今回ご紹介する原作との比較は——
『塔の上のラプンツェル』です!
『塔の上のラプンツェル』は、みなさんもご存じの通り
ディズニー長編アニメーションの記念すべき第50作目となる作品です
50作目と聞くだけで、ディズニーアニメーションの長い歴史が感じられますよね
実はディズニー長編アニメーションの歴史は
いくつかの「黄金期」と「暗黒期」に区分することができます
以下に、主な時代区分をご紹介します。
ディズニー長編アニメーションの歴史
1.【1937年〜1940年代】ウォルト・ディズニーの挑戦期
(白雪姫~バンビまで)
2.【1940年代】第一の暗黒期
『ラテン・アメリカの旅』〜『イカボードとトード氏』
3.【1950年代〜1968年】ウォルト・ディズニーの黄金期
『シンデレラ』〜『ジャングル・ブック』
4.【1970年代〜1980年代】第二暗黒期
『おしゃれキャット』〜『オリバー』
5.【1990年代~2000年代初頭】ディズニー・ルネッサンス
『リトル・マーメイド』〜『ターザン』
6.【2000年代】第三暗黒期
『ファンタジア2000』〜『プリンセスと魔法のキス』
7.【2010年代~現在】CG時代の到来
『塔の上のラプンツェル』以降
『塔の上のラプンツェル』は、ディズニー長編アニメーションにおいて
「白雪姫」、「シンデレラ」、「リトル・マーメイド」と並ぶ
重要な“ターニングポイント”となった作品です
そこで今回は
原作とアニメ版の違いに加えて
なぜこの作品がディズニー長編アニメーションにとって
転換点となったのかについてもご紹介していきたいと思います
それでは、さっそく見ていきましょう!
原作とアニメの比較
2000年代に制作されたディズニー作品の中で、原作が童話・おとぎ話であるものは
過去の作品と比べても原作の要素がごくわずかしか残っていないことが多く見られます
『塔の上のラプンツェル』もそのひとつ
そもそも原作の『ラプンツェル』は、アニメ版と比べて非常に短い物語です
そこで今回は
原作『ラプンツェル』の流れに沿って、アニメとの違いを紹介していきます
もしかしたら、みなさんにとって知らなかった意外な発見があるかもしれませんよ!
ラプンツェルの誕生
原作:庶民の家庭に生まれる
アニメ版:王家の娘として生まれる
ラプンツェルをさらった悪役
原作:魔法使いのおばあさん
アニメ版:ゴーテル
さらわれた理由
原作:妻が魔女の育てた野菜(ラプンツェル)を欲しがり、代わりに娘を差し出した
アニメ版:ラプンツェルの魔法の髪で若さを保ちたかったから
ラプンツェルの恋人
原作:王子
アニメ版:お尋ね者のフリン・ライダー(本名:ユージーン)
恋人はどうやって塔に入った?
原作:ラプンツェルの歌声を聞いて塔を発見。魔女の出入りを見て真似た
アニメ版:警備兵(馬のマックス)から逃げている途中、偶然見つけて自力で登った
ラプンツェルは塔から出たがっていた?
原作:出たがっている描写は特にない
アニメ版:外の世界に憧れ、ゴーテルの支配に疑問を持つようになる
恋人と出会ったその後
原作:毎晩王子が塔を訪れ、ラプンツェルは妊娠する
アニメ版:ラプンツェルとフリンは塔を脱出し冒険の旅へ
魔女(ゴーテル)のその後
原作:ラプンツェルに恋人がいると知り、髪を切って彼女を荒野に追放。王子を塔から突き落とし、失明させる
アニメ版:ラプンツェルを追いかけ続けるが、最終的に転落し消滅(明言されていない)
物語の結末
原作:失明した王子が3年彷徨い、荒野でラプンツェルと再会。彼女の涙で視力が戻り、二人と子どもは幸せに暮らす
アニメ版:ゴーテルに刺されたユージーンは絶命するが、ラプンツェルの涙で蘇生。彼女は王家に戻り、ハッピーエンドを迎える
アニメ版しか観たことがない方にとっては
原作はあまりに短く、あっさりした展開に感じるかもしれません(実際、僕もそう感じました)
みなさんは、どれくらいご存じでしたか?
意外な発見はありましたか?
こうして比較してみると
『塔の上のラプンツェル』は原作に比べて冒険要素やロマンスが大きく強化された作品であることがわかります
もしこの記事を読んで
「原作を確かめてみたくなった」
「意外な違いにびっくりして、読んでみたくなった」
そんなふうに思っていただけたなら
ぜひ一度、原作『ラプンツェル』にも触れてみてくださいね!
| グリム童話集(1) (偕成社文庫) [ ヤーコプ・グリム ] 価格:1,100円(税込、送料無料) (2025/8/3時点) 楽天で購入 |
さて、最初にも触れた通り
『塔の上のラプンツェル』は、ディズニー長編アニメーションの第50作目にして
重要な“ターニングポイント”となった作品です
次の章では
なぜこの作品が、ディズニー作品における大きな転換期となったのか――
その理由を詳しく解説していきます
手描きからCGへ――ディズニーアニメーションの転換点
最初に結論からお伝えすると
『塔の上のラプンツェル』は
ディズニー長編アニメーションが完全にCGへと舵を切った最初の作品です
実は、ディズニー作品(実写やピクサー作品も含めると)、CGの歴史はとても長くなります
たとえば――
世界で初めてCGを導入した映画は『トロン』
そして、世界初のフルCGアニメーション映画は、ピクサーの『トイ・ストーリー』
これらはすでにご存じの方も多いかもしれませんね
しかし、これらすべてを解説しようとすると
それだけで一冊の本ができてしまうほどのボリュームになりますので
今回は、ディズニー“長編アニメーション”に限定して、CGの歴史をお話ししていきたいと思います
最初にCGが使われたのは?
ディズニー長編アニメーションで初めてCGが導入された作品――
それはなんと『美女と野獣』なんです!
使われているのは、ベルと野獣がダンスホールで踊る名シーン
背景の大きなホールが、実はCGで描かれているんです
手描きととてもよくなじんでいるため、気づきにくいかもしれませんが
よーく見てみると、背景のカメラワークなどにCGならではの特徴が見て取れます
もし「初めて知った!」という方は、そのシーンだけでもぜひ見返してみてくださいね
他にも――
・『アラジン』の魔法の洞窟
・『ノートルダムの鐘』のお祭りの群衆
など、ディズニー・ルネサンス期の作品にも部分的にCGが取り入れられています
2000年代、そして変革の年「2006年」
2000年代に入ると、CGの使用はさらに本格化します
たとえば…
・『ファンタジア2000』では、一部の短編作品にCGが使われ
・『ダイナソー』ではキャラクターがCG、背景が実写という形式で制作されました
そして、2006年に大きな転機が訪れます
より本格的に使われるようになっていきました
そして2006年に変革が訪れます
ウォルト・ディズニー・スタジオがピクサーを買収したのです
これにより、ピクサーの創設者であり、『トイ・ストーリー』の生みの親であるジョン・ラセターが
ディズニーアニメーションのチーフ・クリエイティブ・オフィサーに就任しました
ディズニー初のフルCGアニメーション作品は?
では、2006年に公開されたディズニー長編アニメーション作品、ご存じでしょうか?
その作品こそが――
「チキン・リトル」です!
『チキン・リトル』は、ディズニー長編アニメーション史上初のフルCG作品として制作・公開されました
ここから、ディズニー・アニメーション・スタジオは本格的な“変革の時代”へと突入します
試行錯誤と「手描き」の終焉
その後、ディズニーは手描きアニメーションとCGアニメーションを交互に制作しながら
現代に合う新しいスタイルを模索していきました
その流れの中で制作されたのが――
『プリンセスと魔法のキス』
この作品では、ウォルトの時代から続くおとぎ話を題材にし
ディズニー・ルネサンスで築いたミュージカル要素も取り入れるなど
原点回帰を意識した作品でした
しかし、残念ながら興行的には振るわず、手描きアニメーションはここで終焉を迎えます
(※実質的な最後は『くまのプーさん』ですが)
そして誕生した『塔の上のラプンツェル』
その翌年――
『プリンセスと魔法のキス』と同じく
おとぎ話が題材で、ミュージカル調の演出
しかし、最新のCG技術を取り入れた作品として生まれたのが――
『塔の上のラプンツェル』です!
この作品は興行的にも大成功を収め
ディズニーはここから本格的にCGアニメーションへと完全移行していくことになります
そしてその流れの中で――
・『アナと雪の女王』
・『ズートピア』
・『モアナと伝説の海』
など、数々の大ヒット作が生まれていったのです
| 【特典】塔の上のラプンツェル MovieNEX(『星つなぎのエリオ』劇場公開記念 オリジナルスライダーポーチ) [ マンディ・ムーア ] 価格:3,212円(税込、送料無料) (2025/8/5時点) 楽天で購入 |
『塔の上のラプンツェル』が示した、ディズニーの“これから”
『塔の上のラプンツェル』は
ウォルト時代の礎である“おとぎ話・童話”を題材にし
ディズニー・ルネサンス期に築かれたミュージカル調のスタイルに
最新のCG技術を融合させた作品です
つまり、過去と現在、それぞれの“良さ”を組み合わせて作り上げられた
ディズニーアニメーションの集大成とも言える作品なんですね
だからこそ、『塔の上のラプンツェル』は
ディズニー・スタジオにとって大きなターニングポイントとなったのです
みなさんは、『塔の上のラプンツェル』のどんなところが好きですか?
僕自身、ラプンツェルはプリンセスの中でも一番好きなキャラクターです。
(とくに、明るくて前向きな性格が!)
ぜひ、みなさんの「好きなポイント」もコメント欄で教えてくださいね!
そしてこの記事を読んで
「原作を読んでみたくなった」
「もう一度、アニメ版を見直したくなった」
そんなふうに思っていただけた方は
ぜひこの機会に、原作とアニメ、どちらも楽しんでみてください!
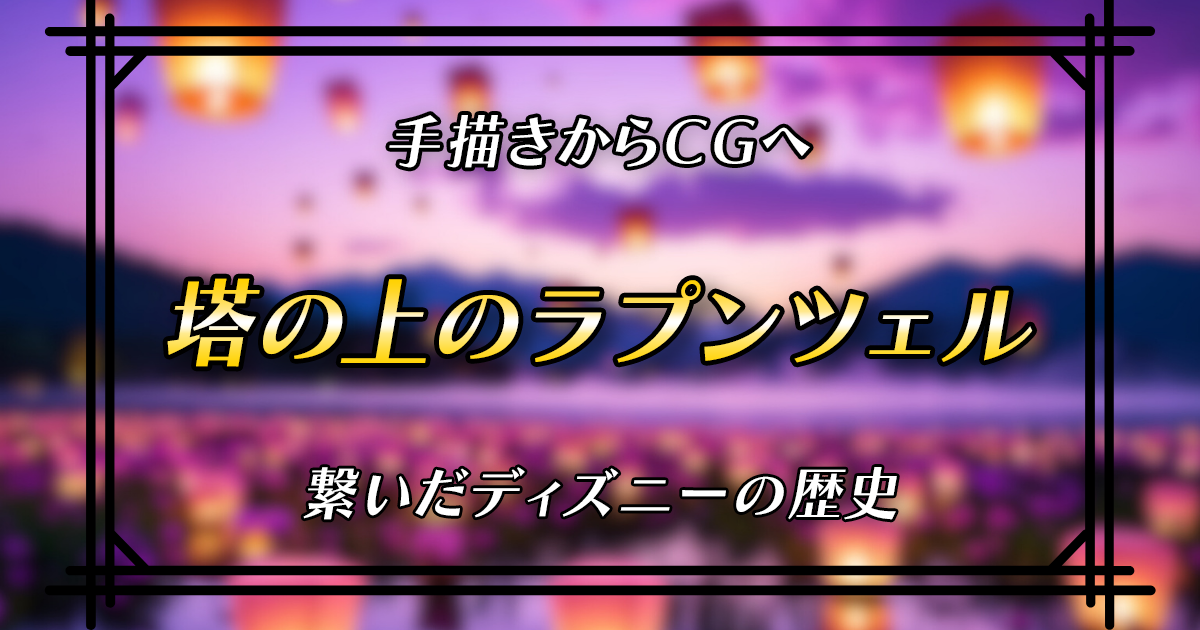

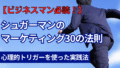
コメント